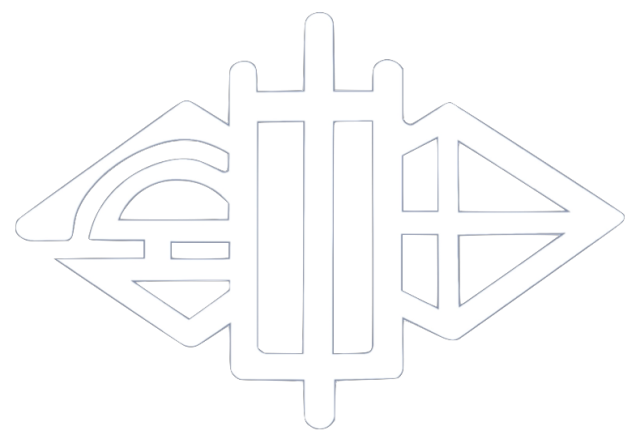「絆」ボランティアに行ってきました。
- 公開日
- 2012/01/30
- 更新日
- 2012/01/30
その他
本校の3人の先生が、宮城県南三陸町にボランティアに出かけました。ボランティアの内容は、南三陸町の志津川仮設住宅付近の津波で流されてしまった生活用の橋の再建でした。山から材木を切り出し、人が通れるような橋を土曜日1日がかりで造ったそうです。日曜日には、多くの児童や先生が流されて命を失った石巻市立大川小学校にも立ち寄って冥福を祈ったそうです。現地の方からは、材木の切れ端でつくった「絆」のオブジェをいただきました。早速、宮田中学校の玄関に飾らせていただきました。
3人の先生の感想は、下の通りです。
今回は、宮城県の南三陸町でのボランティア活動に参加させていただきました。未だ震災の爪痕が色濃く残り、行く先々で言葉を失いました。今回は一日かけ、杉の木を用いて生活道路用の橋を作らせていただきました。とても大変な作業で、思うように進まず、無力感に襲われました。しかし、参加者全員が一致団結し、ようやく橋が完成した時には、「一人ではできないことも、みんなで力を合わせればできるんだ。」と強く感じました。
また、現地の方より、震災当日から復興に向けての日々について、貴重なお話を伺うことができました。その中で、「震災前と震災後で一番変わってしまったのは、人の心だ。」という言葉が、私の胸に強く響きました。津波によって町の様子も大きく変わりましたが、先が見えなくなった状況で、人々の心から希望が消えたこと、そして人と人とのつながりが途絶えてしまったことが、一番の変化だったと教えてくださいました。今、被災地の方々だけでなく、支援をする側も共に「絆」を深めていくことが、復興につながるのだと思います。
私は17年前に阪神大震災で被災し、その際、多くの方々に支援していただきました。そのおかげで、今の私があり、そして美しい故郷があります。これからも、今回のボランティアという形だけでなく、今自分ができることをして、被災地復興へ少しでも協力していけたらと思います。(桑畑 祐希)
先週、宮城県南三陸町でボランティア活動をさせて頂きました。今回、自分たちが行った活動は川に生活道路用の橋を架けることでした。木を切り倒し、皮を削り、運び、橋を架けるというものでしたが、川辺まで運ぶことに苦労しました。完成した橋を見たときには、達成感に包まれました。
その後、現地の方から津波のときの様子を拝聴し、その中で一番心に残ったことは「津波によって、僕は体だけを残してすべてを失った。」というものでした。その言葉は、「自分の家や仕事はもちろんのこと、周りの方との関係まで変わってしまった。」ということでした。お話を聞きながら、「もし自分が災害だけでなく、病気や事故によって、親族や職場の方々との関係が変わってしまったらどうなってしまうのか。」ということを考えていました。
東日本大震災から10か月程たちましたが、実際に見てみると、被災地の細かい瓦礫はまだまだ残っているのが現状でした。しかし、もう復興は終わったと考え、ボランティア活動に参加して実際に活動する人たちの数はずいぶん減ったらしいのですが、1日も早く復興が進み、東北が元気になることを祈っています。(廣田 貴之)
今回、「第4回便教会ボランティアバス」に参加させていただき、貴重な体験をしました。
ボランティアとして行ったことは、「生活道路用の橋を架ける」というものでしたが、山へ入り、杉の木を切り倒し、皮をむき、大きい物は10人がかりで、小さい物でも3人がかりで運び、橋を架けました。皮をむいたり、運び出したりすることはとても重労働で大変でしたが、橋がだんだんできてくるととても嬉しくなり、完成したときには達成感でいっぱいになりました。
一方で、まだ瓦礫の山が残っていたり、建物の基礎だけがそのままになっていたりと復興の手がまだまだ及んでいない現状に心が締め付けられるような思いでした。
最も衝撃的だったことは、廃墟と化した建物の上にまだバスや車が乗ったままになっていることでした。
最近では福島県の原子力発電所関連の情報しか流れなくなってきていますが、津波被害の復興もまだまだ進んでいないというのが現状です。こういったことをたくさんの人が知り、1日も早く復興の手が伸びることを祈っています。(今枝 敏樹)