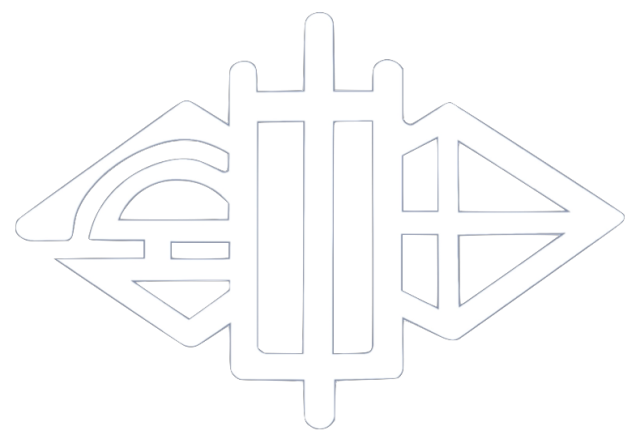「沖縄の島守」島田叡(あきら)知事を想う
- 公開日
- 2013/08/10
- 更新日
- 2013/08/10
校長室から
太平洋戦争の末期、昭和20年1月、沖縄県知事の任命を受け島田叡(あきら)さんが赴任されました。 その当時の沖縄は空襲が激しさを増し、米軍の侵攻上陸も必ず来るとみられていました。赴任すれば確実に死ぬという情勢に、任務辞退を勧める親友・周囲の声に対し、島田さんは、
「私が行かないと断ると、誰かが行かなければならない。私は死にたくないので、代わりに君行って死んでくれなんて云えないじゃないか」と沖縄へ出かけました。
昼夜にわたる艦砲射撃、空爆が相次ぐ沖縄で、県民生活の安全や食糧確保、また県民の本土疎開・避難などに尽くされました。特に県民を兵隊さんとは一緒にしないように考えられてみえました。一緒に死なせたくなかった島田さんの考えがよくわかります。
4月に入って大量の米軍が沖縄本島に上陸し、各地で戦闘は激しく、軍も島民にも多くの犠牲者が出ました。軍は言うに及ばす県庁等の役所も、島民と同様に洞窟から洞窟へ避難して渡り歩かれるのですが、6月には南部の丘に追い詰められました。そこで県庁組織の解散を宣言し、共に死ぬと退去を拒(こば)む部下たちを
「生きのびて沖縄のために尽くしなさい」
と無理矢理追い出し、県民の保護に専心されていた荒井退造警察部長と共に濠に留まり、壮絶な最期を遂げられました。島田叡さん、その時45歳。
この当時の日本は「生きて捕虜となるな」、「最後まで戦え」「玉砕こそ日本人の誉れ」
の考えが徹底されていました。そんな状態の中で、「生きろ」「生き延びろ」「白旗を振れば殺されることはない」とよくぞ言われたと思います。知れれば自分も銃殺ではないでしょうか。偉大なる沖縄の知事さんでした。わずか5ヶ月足らずの沖縄での島田さんの行動が「沖縄の島守」として、戦後多くの県民に慕われ続けているのは島田さんの「生きろ」その言葉が沖縄の島民の方に響いたのだと思います。