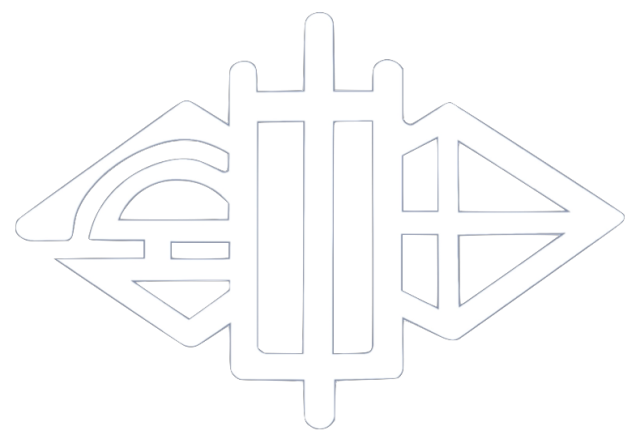丸餅と角餅の境界線
- 公開日
- 2014/01/02
- 更新日
- 2014/01/02
その他
西日本は丸餅、東日本は角餅と言われていますが、そもそも餅は、円満の意味をもつ縁起物の丸餅だったようです。切り餅が出てきた背景は、生産性の問題と言われています。ひとつひとつ丸めるよりも、平らに伸ばした餅を切り分けた方が早くできるというわけです。人口増加の激しかった江戸時代は、大量の餅を作らなければならず、切り餅が主流になったわけです。要は、嗜好などという問題ではなく、そうせざるを得なかったのです。
さて、丸餅と角餅の境界線をこのあたりで考えてみると、三重は北から、四日市は混在、鈴鹿は切り餅、津は切り餅、名張・伊賀は丸餅、松坂は切り餅、伊勢は混在という状況です。滋賀県と三重県は、昔の藩によって異なるようで、徳川派は角餅、豊臣派は丸餅という説もあります。