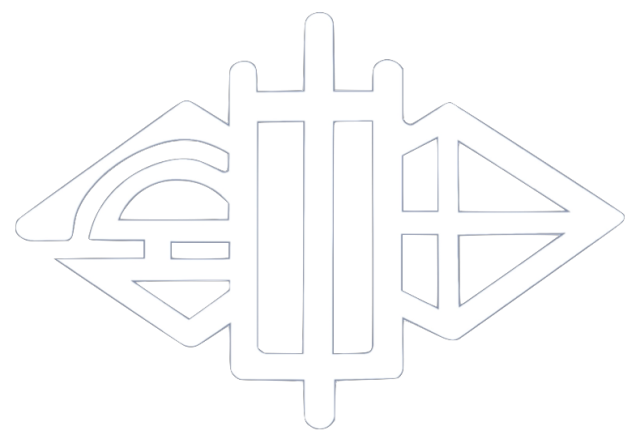徳川家康 「鳴かざれば鳴くまで待とうほととぎす」はどこから来る?
- 公開日
- 2016/08/15
- 更新日
- 2016/08/15
校長室から
豊臣秀吉, 「鳴かざれば鳴かせてみようほととぎす」に対し徳川家康は「鳴かざれば鳴くまで待とうほととぎす」とうたっています。
この背景は何なんでしょうか。昨夜の真田丸でついに豊臣秀吉が亡くなりましたが、家康の有利な面を改めて感じ、この俳句の怖さを知りました。
ひとつは豊臣秀吉より若いということです。豊臣秀吉は1537年生まれ、徳川家康は1543年生まれで豊臣秀吉と徳川家康は6歳差があるのです。さらに秀吉は体があまり丈夫でないと判断されます。(飲み過ぎ・・・。)一方、家康は漢方などに興味をもち、自分の健康に心がけます。
もう一つは徳川家康は生涯で11男5女の16人の子供に恵まれるのですが、豊臣秀吉は3男1女で側室・南殿との間に1男1女、淀殿との間に2男の子でした。でも側室の男児は6歳で亡くなっています。女児は不明、淀殿との間の最初の子、豊臣鶴松は3歳で病死です。つまり、豊臣秀吉は子が一人しかいないのです。
さらに徳川家康は娘を有力な大名家に嫁がせ、縁を深めていきます。昨夜も放送されていましたが伊達家と縁組を決めていました。
この推理が正しいかどうかはわかりませんが、歴史を好きになるとおもしろくなるのもこんな面ではないでしょうか。
「鳴かざれば鳴くまで待とうほととぎす」家康はしたたかだったのです。