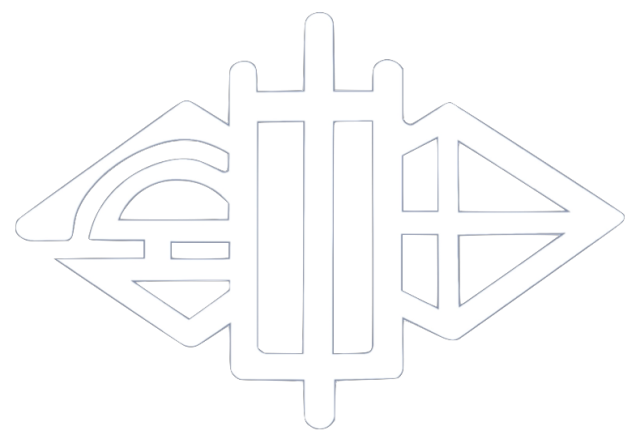阪神大震災での悲しい出来事 『一人の警察官の手記より』
- 公開日
- 2017/01/18
- 更新日
- 2017/01/18
校長室から
阪神大震災から二ヶ月ぐらいして読売新聞に一人の警察官の手記が掲載されました。その手記はあまりにも悲しく、母が子を思う気持ちや命の尊さを我々に考えさせるものでした。多くの学校が道徳の授業に取り入れましたが、もう教育現場では扱われなくなっていると思います。
ふと、みなさんに知って頂きたく掲載します。
【一人の警察官の手記より】
任務は長田署管内の救助活動・遺体捜索。そして村野工高体育館における遺体管理と検視業務の補助であった。
仮の遺体安置所になっていた体育館は、沢山の遺体と、それに付き添う家族であふれていた。そんな中で、私は一人の少女に釘づけになった。その少女は、膝の前に置いた焼け焦げた「ナベ」にじっと見入っていた。泣くでもなく、身動きもせず、だだじっと見入っていた。
私は、その少女に引かれるように近寄っていった。「ナベ」の中には小さな遺骨が置かれていた。「どうしたの」。思わず問いかけた私の一言がその少女を泣かせてしまった。どっとあふれだした涙を拭おうともせず、懸命に私の目を見つめ、とぎれとぎれに語り続けた。「ナベ」の中は、少女が拾い集めた母親の遺骨であるという。
その夜(一月十六日)も少女は母に抱かれるように、一階の居間で眠っていた。何が起こったかも解らないまま、気が付いたときは母とともに壊れた家の下敷きになって、身動きもできない状態になっていた。
それでも少女は少しずつ体をずらし、何時間もかけて脱出できた。家の前に立って、何が何だか解らないまま、どの家も倒れているのを見た。しばらくして、母が家のなかにとり残されていることに気が付いた。
「おかあさんを助けて」「助けてお願い」
大人たちに片っ端からしがみ付き、声をかぎりに叫び続けた。
誰にもその叫びは聞こえなかった。声は届かなかった。
迫ってくる火事に、母を助けるのは自分しかいないと哀しい決断を強いられた。母を呼び続け、懸命に家具を押し退け、瓦礫を放り投げ、一歩一歩母に近づいていった。やっとの思いで、母の手を捜し当てた。姿は見えなかった。
母の手を見つけたとたん、その手を握り締めた。その時、少女の手は血塗れになっていることに気が付いた。
「おかあさん」「おかあさん」「おかあさん」
手を握り締め、泣きながら叫び続けるだけであった。
火事は間近に迫っていた。火事の音が聞こえ、熱くなってきた。母は懸命に語りかけたが、かぼそい声で少女には聞こえなかった。「おかあさん」「おかあさん」と叫び続ける少女に、名前を呼ぶ母の声がようやく聞こえた。
「ありがとう。もう逃げなさい」
母は握っていた手を放した。
熱かった。恐かった。夢中で逃げた。すぐに、母を抱え込んだまま、我が家が燃えだした。燃え盛る我が家をいつまでも立ち尽くし、見続けた。声もでなかった。涙もでなかった。
翌日、何をしたか、どこに居たか、覚えていない。翌々日、少女は一人で母を探し求めた。そして見つけだした。少女は、いま一人で見つけだした母を「ナベ」に入れ、守り続けている。
語り続ける少女の目から、いつの間にか涙が消えていた。ただ聞くだけの私は、声もでず、涙だけがあふれ続けた。母と二人。この少女がどんな生活をしていたか私は知らない。一人になったこの少女に、どんな生活が待っているか、私には解らない。
『この少女に神の加護がありますように』
生まれて初めて「神」に祈った。
この少女に、慰めの言葉も、激励の言葉も何も言えなかった。何度も何度もうなずくだけで、少女の前を逃げた。少女は、最後まで、私の目を見続け、語り、そして語り終えた。その目は、もっと多くのことを、私に語りかけ、今も続いている。目は生きていた。
哀しいと思った。強いと思った。
少女は小学校三、四年生くらいで、付き添う大人の姿はなかった。警部補は別れてから、少女の名前を聞いていないことに気付いた。その後の少女の消息はわからない。